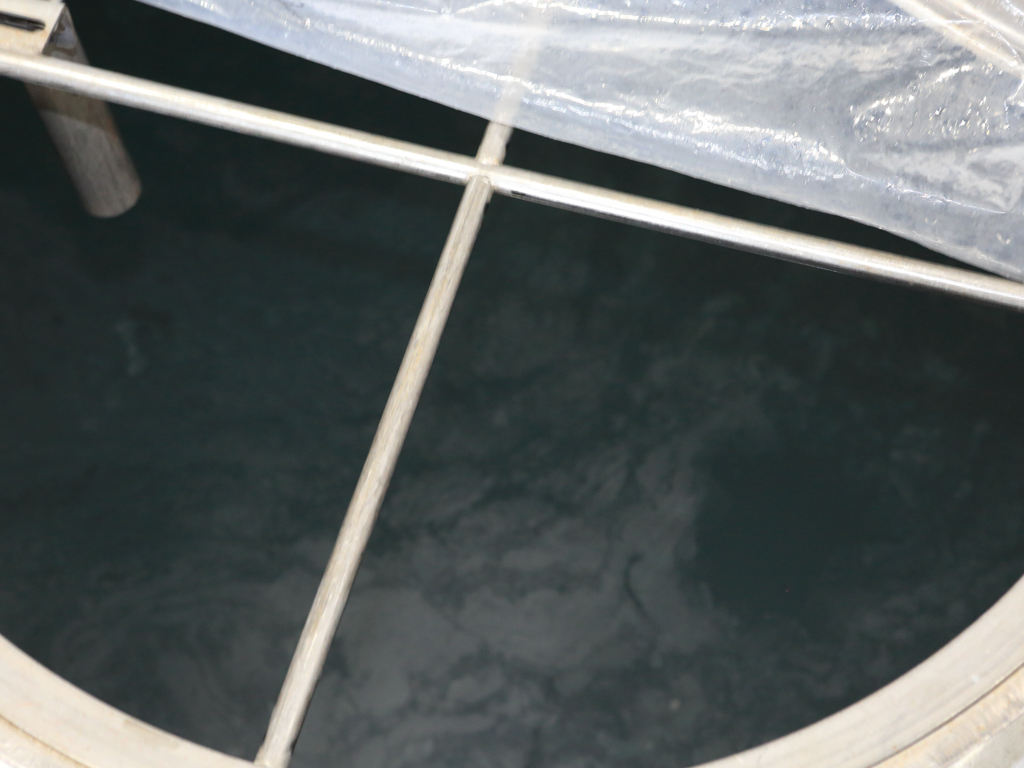世界のソムリエが評価した蔵の新たな挑戦
「私は芋臭い焼酎が飲みたかった」
「ツン」「ミトラ」「ぷう」。女子受けしそうなかわいいラベルだけど、いずれも強烈なインパクトのある芋焼酎だ。ただ、鹿児島市の酒店「たにもと屋」に並ぶ一升瓶を見たけれど、製造元の田崎酒造のホームページには一切、出ていない。
なぜだろう? 鹿児島県いちき串木野市にある田崎酒造を訪ね、杜氏の野崎充紀さんに聞いてみた。
熟成重視の蔵がひっそりと販売する新酒
「うちは、あくまで『七夕(たなばた)』の蔵なんです」。野崎さんは、田崎酒造の代表銘柄を挙げて説明を始めた。「長期熟成の芋焼酎にこだわり、新酒を出さない蔵としてやってきました。ツン、ミトラ、ぷうは私が2年前に立ち上げたブランドなんですが、新焼酎なんです。つまり蔵の方針と違うのです。だから、積極的に表に出していないんです」
「薩摩七夕」と言えば、世界的なワインソムリエである田崎真也さんがおススメしたことで知られる、田崎酒造の看板の芋焼酎。ナッツのような熟成香とまろやかな口当たりが特徴である。蔵のレギュラー酒とは真逆の焼酎をなぜ造ろうと思ったのか?
蔵の方針と真逆の「クセのある焼酎」
「熟成焼酎はとても魅力的なものです。原酒を寝かせることで、芋臭さを抑え、スマートで飲みやすい焼酎になります。うちの七夕は万人に好んでもらえる味わいと自負しています」。野崎さんは七夕には七夕の素晴らしさがあると断りつつ、続けた。「私は焼酎の造り手ですが、造り手である前に、焼酎を飲むのが好きな人間です。だったら、自分好みの個性ある焼酎をつくってみたいと思ったんです。私が飲みたいのは、昔ながらの芋臭い焼酎なんです」
蔵伝統の味は大事だ。でも、ふつふつと湧き上がる杜氏としての挑戦心は抑えることができなかった。「女性でも飲みやすい焼酎、とよく表現されますよね。私はその表現は間違ってると思うんです。『本当に女性はクセがある焼酎は飲めないの?』って思いませんか。クセがあるのが嫌なのなら、世の中の女性はみんな白ワインしか飲まないんじゃないかな。でも違うでしょう。例えるなら、私は白ワインじゃなくて、赤ワインをつくってみたいと思ったんです」
「昔は町ごとに個性的な芋焼酎があったもんです。あっちの焼酎は甘か、あっちのは辛か、あっちのは臭かっていう具合にね」と野崎さんは懐かしむ。確かに、数十年前にあった「芋くさ~い」焼酎はお目にかかれない。消費者の中には「何を飲んでも一緒」という声もある。そんなことを言われたら「造り手としては寂しい」。だから、さつま芋という原料由来の個性を思う存分、出してみたいと思った。
「ツン」「みとら」「ぷう」。3つの芋の味わい
「ツン」は蒸した黄金千貫を昔ながらの風味に仕上げ、「もともとあった鹿児島の地焼酎」を再現してみた。「みとら」は紅さつまの焼き芋を焼酎に、「ぷう」は熟した黄金千貫を日本酒酵母で仕込んでいる。「蒸す、焼く、熟す。自分が飲んでみたい焼酎を想像しながら、3つの芋の味わいに挑戦してみました」
ちなみに、「ツン」は西郷隆盛の愛犬の名前をもらい、「みとら」は野崎さんの飼い猫の名から。「ぷう」は「夏の青空に雲がぷう~と流れる様を見てということで(笑)」。
取材日は、タンクからツンの原酒をすくい、香りをかがせてもらった。モワッとパンチのある香りが漂ってきた。芋の心地よい果実香が鼻を抜ける。昔の「臭い」という感じではない。「今時、どこの蔵もやらないでしょう」という製法で、酵母にストレスを加えたり、蒸留法を工夫してみたりして、インパクトのある芋の風味を引き出した。
「お湯割りがうまい焼酎は、うまい」
野崎さんの考え方は、お湯割りでうまい焼酎を造れば、水割りにしても、ロックにしてもうまい。「私はお湯割りにした時にアルコール臭が立つ焼酎は飲めない。悪酔いしてしてしまうので、晩酌ができないんです。実は、アルコール臭が立たないようにすると、どんどん昔ながらの造り方になっていくんです。批判されることはあるんですけど、仕方ないですよ。私が飲みたい焼酎なんですから」
ブレンドを一切せず、毎年味が違う「ツン」
焼酎はウイスキーなどと同じ蒸留酒なので、一般的に出荷する商品は、様々な原酒をブレンドして味を整える。ただ、「ツン」はブレンドを一切していない。「造り手としては、絶対ブレンドした方がいいですよ。毎年の味を統一しないと、クレームのもとですから」と野崎さん。「でもね。毎年の仕込みの中では必ずドラマやハプニングがあって、思い入れのある原酒ができるんです。それに、前年の原酒を混ぜるのはちょっとね。ブレンドしないから、来年はもっと良いものを造ってやろうという気になります。『おいしい』と言われたらもっと、うまいものを造ってやりたい。常に上を目指していきたいからブレンドしないんです」
味が動く、どんどんうまくなる
野崎さんの造る焼酎は、味がどんどん動いていく。僕も栓を抜いて口に含んだ時、荒々しいなと思っていた「ツン」を2ヶ月ぐらい置いていたら、味が落ち着いて、口の中に芋の香りがいっぱいに広がった。「焼酎は良い方向に味を動かさないといけないんです」と杜氏。ただ、毎年味も変わるし、味も動いていくから、クレームの対象になりかねない。だから、「ツン」「みとら」「ぷう」は焼酎の特徴をわかっている対面販売の酒販店にしか置いていないという。
「造り手」としての矜持が会社を動かす
野崎さんの思いは、会社の方針とは違う。よく社長が許してくれたものだと聞くと、「本当に社長には、感謝しています。今は私が責任を取れる範囲で、身の丈にあった量しか造っていません。度胸があれば、たくさんの量を造るんですけどね(笑)」。よっぽど、信頼されているのだろう。
「熟成いも焼酎」を掲げる田崎酒造の方針に、逆行する新酒の焼酎。野崎さんは杜氏と言えども、社員の1人にすぎない。
だが、たとえ蔵の方向性と違っても、自ら飲みたい焼酎を追求する。焼酎造りのプロとしての矜持。こんなに気骨のある杜氏が鹿児島にいたのか。なんだか、うれしくなった。
田崎酒造
http://tasaki-shuzo.jp
鹿児島県いちき串木野市大里696
0996-36-3000
1887年(明治20年)創業当時から造り続けている「薩摩七夕」は、黄金千貫芋を白麹で仕込んでいる。名前の由来はいちき串木野市に伝わる「七夕踊」から。黒麹でつくった「薩摩黒七夕」もある。いずれも熟成にこだわっている。